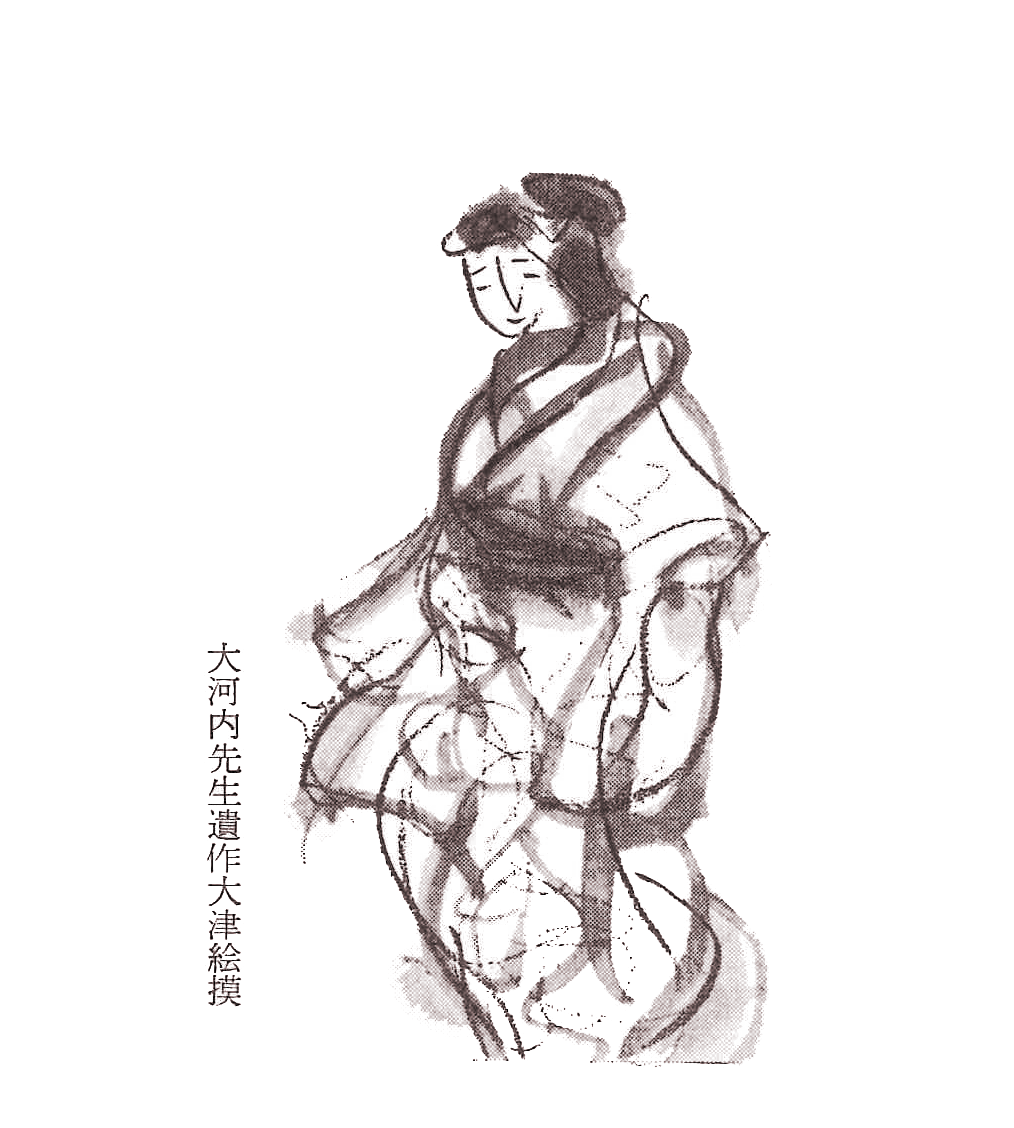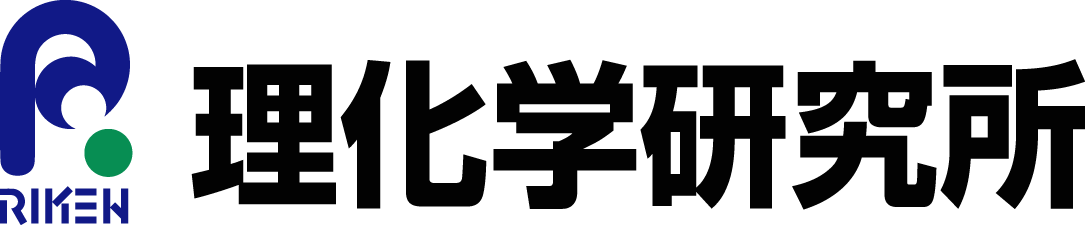大河内記念会について
ごあいさつ
 この度令和7年6月をもって、記念会発展にご功績のありました前任の山崎弘郎先生を引き継いで理事長を拝命いたしました。記念会初代の辻二郎理事長から数えて10代目となる歴史の重みを感じつつ、微力ながら最善を尽くして記念会伝統の継承・発展へ向けて励む所存でございます。
大河内記念会は、科学によって新たなる技術を創造し、我が国独自の産業を打ち立て、よって国際競争力を高めるという故大河内正敏博士の志を継ぎ、生産のための科学技術の振興をはかるべく創設された「大河内賞」の贈賞事業の運営を行っています。大河内賞は、昭和30(1955)年5月7日に第1回の贈賞を行って以来、令和7(2025)年3月まで、71回を数え、基礎、応用、実用化から製品化にかかる生産工学に資する優秀な成果を対象とする賞として各界から高い評価をいただいているところです。
20世紀末期から21世紀に入り科学技術分野の発展は目覚ましいものであり、特に生産工学においては従来型技術への見直しにおけるこれまでにはなかった展開が国際競争力を激化させてきています。例えば、素形材の製造プロセスにおける組成制御や不純物の低減と精密な制御を可能とするオンラインでの分析・制御技術、また加工加熱・冷却手法の精緻化による様々な巧妙な組織制御等々の技術に加えて、製品の安定した機能の発現を担保するために必要な一連の製造過程を最適化するためのシステム構成の高性能化等も要求されて来ています。
このように大河内賞70年の歴史の中で、我が国の生産工学の姿が変ってきたと認識しており、また更に新しい時代に生まれる優れた技術に対して、しっかり評価し、贈賞する必要があると考えています。例えば、ある既存の生産工学システムの機能を画期的に高める手法として、思いがけない発想に基づいた仕組みをシステムに取り入れることができるとすれば世界を変える大きなイノベーションに繋がる可能性があります。このような発想に至るための有効な手段としては、現在の研究開発グループの中だけでなく、日頃から国内外の異分野の研究者・技術者との融合を図る仕組みを持ち、進めることにより可能性は十分に高まると考えます。特に若い研究者たちがこのような発想を得て育んだ成果について奨励し、評価して行きたいと考えているところです。
この度令和7年6月をもって、記念会発展にご功績のありました前任の山崎弘郎先生を引き継いで理事長を拝命いたしました。記念会初代の辻二郎理事長から数えて10代目となる歴史の重みを感じつつ、微力ながら最善を尽くして記念会伝統の継承・発展へ向けて励む所存でございます。
大河内記念会は、科学によって新たなる技術を創造し、我が国独自の産業を打ち立て、よって国際競争力を高めるという故大河内正敏博士の志を継ぎ、生産のための科学技術の振興をはかるべく創設された「大河内賞」の贈賞事業の運営を行っています。大河内賞は、昭和30(1955)年5月7日に第1回の贈賞を行って以来、令和7(2025)年3月まで、71回を数え、基礎、応用、実用化から製品化にかかる生産工学に資する優秀な成果を対象とする賞として各界から高い評価をいただいているところです。
20世紀末期から21世紀に入り科学技術分野の発展は目覚ましいものであり、特に生産工学においては従来型技術への見直しにおけるこれまでにはなかった展開が国際競争力を激化させてきています。例えば、素形材の製造プロセスにおける組成制御や不純物の低減と精密な制御を可能とするオンラインでの分析・制御技術、また加工加熱・冷却手法の精緻化による様々な巧妙な組織制御等々の技術に加えて、製品の安定した機能の発現を担保するために必要な一連の製造過程を最適化するためのシステム構成の高性能化等も要求されて来ています。
このように大河内賞70年の歴史の中で、我が国の生産工学の姿が変ってきたと認識しており、また更に新しい時代に生まれる優れた技術に対して、しっかり評価し、贈賞する必要があると考えています。例えば、ある既存の生産工学システムの機能を画期的に高める手法として、思いがけない発想に基づいた仕組みをシステムに取り入れることができるとすれば世界を変える大きなイノベーションに繋がる可能性があります。このような発想に至るための有効な手段としては、現在の研究開発グループの中だけでなく、日頃から国内外の異分野の研究者・技術者との融合を図る仕組みを持ち、進めることにより可能性は十分に高まると考えます。特に若い研究者たちがこのような発想を得て育んだ成果について奨励し、評価して行きたいと考えているところです。
多くの研究者、技術者、そして企業にとって、大河内賞の受賞が一つの大きな通過点であり、勲章であり続けられるよう、取り組んでまいりますので何卒ご支援ご鞭撻を頂きたくお願い申し上げます。
令和7(2025)年 6月21日
公益財団法人大河内記念会
理事長 三島 良直
大河内記念会の概要
1.沿革
- 昭和29(1954)年4月大河内記念会設立
事務所を理研合成樹脂株式会社内(中央区銀座)に置く - 8月「大河内正敏・人とその事業」を刊行
- 昭和30(1955)年5月第1回大河内賞贈賞式挙行
- 昭和33(1958)年2月財団法人として認可を受ける
- 昭和35(1960)年3月「受賞業績ダイジェスト」第1集(第1回~第5回受賞)を刊行(以後2年毎に第7集(第16回~第17回受賞)まで刊行)
- 昭和36(1961)年5月大河内賞受賞者の親睦団体「友の会」発足
- 8月事務所を中央区銀座から港区虎ノ門(第5森ビル10階)に移転
- 昭和37(1962)年2月第1回「友の会」(講演会・見学会)大会を理化学研究所(駒込)において開催
- 3月「大河内記念賞・副賞金」が非課税所得として認定される(大蔵省告示第62号 昭和37年3月15日)
- 昭和40(1965)年12月大河内記念会創立10周年記念出版として「大河内賞」を刊行
- 昭和42(1967)年12月「友の会 会報」を創刊
- 昭和43(1968)年5月「大河内記念賞」、「大河内記念技術賞」、「大河内記念生産賞」に加え、「大河内記念生産特賞」を新設
- 昭和45(1970)年9月大河内賞の受賞業績内容の英文報告書「Research and Development in Japan Award: The Okochi Memorial Foundation Prize」を刊行
- 昭和47(1972)年11月「友の会 会報」を「五兆」と改題し「第18回大河内賞受賞業績ダイジェスト」を掲載
- 昭和62(1987)年3月「大河内賞30年のあゆみ」を刊行(大河内賞受賞業績のその後の展開と波及効果を記述したもの)
- 昭和63(1988)年12月「昭和62年度(第34回)大河内賞受賞業績報告書」を刊行(前年度の受賞業績を記載したもの、以後、毎年度発行)
- 平成14(2002)年2月ウエブサイト開設
- 平成19(2007)年5月事務所を第5森ビルから現在地(港区虎ノ門・グランスイート虎ノ門 15 階)に移転
- 平成24(2012)年5月内閣総理大臣の移行認定(平成24年4月25日付)を受け、公益財団法人に移行登記(平成24年5月1日付)
- 令和2(2020)年4月新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、第67回大河内賞の贈賞事業を中止
- 令和6(2024)年12月ウエブサイト全面更新
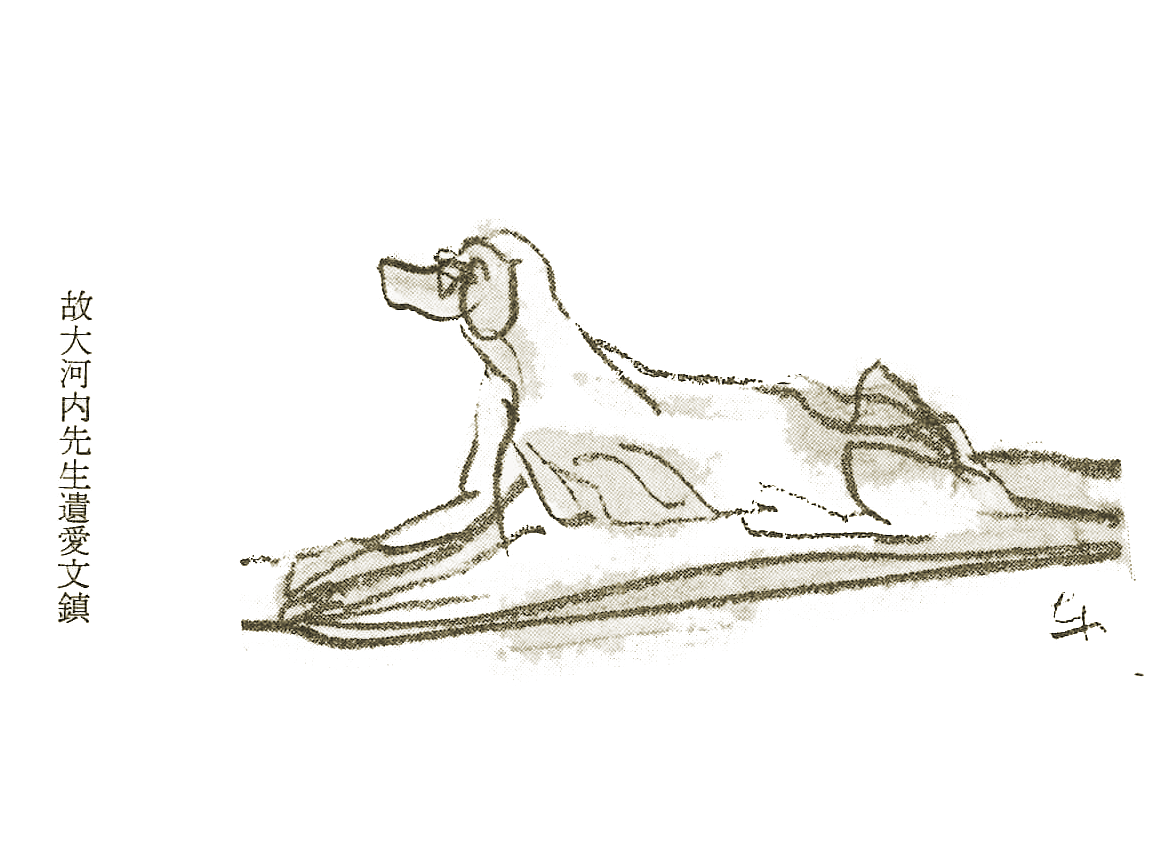
2.設立主旨
財団法人理化学研究所が国の与望をになって創立されたのは第一次世界大戦勃発後間もない大正6年であり、同10年同研究所の第三代所長に選ばれて就任した東京帝国大学教授・工学博士・子爵大河内正敏氏は、やがて一切の他の公職を辞し全力をあげて研究所の経営に没頭、昭和21年所長を退任するまでの在位25年間とその前後、殆ど後半生の一切をこれに捧げられたのであります。
大胆な人事、卓抜な研究推進行政により日本科学界の人材悉く同研究所に集まり、少壮有為の科学者が次々に数多く育成され、世界の水準を抜く優れた研究業績も続々と上がり、昭和19年には所員2千人を擁する一大研究所となりました。
当時として驚くべきこの現象の反面には博士の非凡な才能と実行力と努力とによる「同研究所生れの発明の工業化」活動があり、その成果として産業界にいわゆる理研産業団と呼ばれた60余会社(ビタミン、ピストンリング、計器、感光紙、マグネシウム、アルマイト等多部門にわたる)が設立され、非常時に至る困難な時代に博士自らのユニークな新しい経営リードで独特の飛躍を示し、そこに生れる特許許諾料、実施報酬その他が厖大な研究所経費を賄う財源となったのであります。
博士は早くから、日本の工業の発展に最も重要なものは生産工学であるとの見解からその指導に乗り出されましたが、たまたま戦乱、敗戦と続き、この卓見は十分に世論となるに至りませんでした。昭和27年8月29日、博士が卒然として逝去されるや博士を敬慕する有志相諮り、遺志となった「生産工学の振興」に寄与することによって、日本の産業と科学技術の発展に貢献することを目的として当会を設立したのであります。
設立委員会
3.事業概要
大河内賞贈呈
当記念会創立以来の根幹的事業である。毎年、理工系大学、研究機関、学協会、産業団体、企業等から推薦された生産工学、生産技術の分野の卓越した業績について、大学教授等20余名で構成される「審査委員会」により審査の上、選定された業績に対し大河内賞(記念賞、記念技術賞、生産特賞、生産賞)を贈呈している。
-
受賞業績の出版
毎年、大河内賞受賞業績の技術内容を掲載した「大河内賞受賞業績報告書」を刊行して、国内の大学、研究機関、法人および個人賛助会員、友の会会員等に配布している。このほか、科学技術関係記事および当記念会行事の案内、報告等を掲載する機関誌「五兆」を作成し、上記報告書同様関係方面に配布している。
-
講演会・見学会
当記念会の賛助会員企業と、大河内賞受賞者の連携、親睦団体である「友の会」との技術交流の促進を目的として、毎年1回、講演会、工場見学会を開催している。
-
その他
当記念会の目的達成に必要な賛助金の募集事業を行なっている。
4.所管官庁
内閣府
7.役員等に関する事項
令和 7 年 6 月 21 日開催の評議員会、理事会により、2 期 4 年間理事長を務めた山﨑弘郎が
退任し、三島良直が理事長に就任致しました。
また、藤野直洋、北原武の両常務理事が退任し、富田悟と横井秀俊が就任するとともに、2
名の監事が退任し、新たに 3 名の理事と 1 名の監事が就任しました。
評議員については、1 名の辞任があり、6 名となっております。
<役 員>
| 役 職 名 | 氏 名 | 常勤・非常勤 | 職歴 | |
|
理 事 長 副理事長 常務理事 常務理事 理 事 理 事 理 事 理 事 理 事 監 事 |
三島 良直 中浜 精一 富田 悟 横井 秀俊 古屋 輝夫 加賀屋 悟 伊藤 幸成 中村 聡 宮山 勝 手塚 育志 |
Ph.D 工博 工博 農博 工博 工博 工博 |
非常勤 非常勤 常 勤 非常勤 非常勤 非常勤 非常勤 非常勤 非常勤 非常勤 |
東京工業大学(現東京科学大学)名誉教授 東京工業大学(現東京科学大学)名誉教授 元国立研究開発法人理化学研究所広報室長 東京大学名誉教授、YOKOI Labo代表 大学共同利用機関法人自然科学研究機構理事 国立研究開発法人理化学研究所人事統括本部長 元国立研究開発法人理化学研究所主任研究員 東京工業大学(現東京科学大学)名誉教授 東京大学名誉教授 東京工業大学(現東京科学大学)名誉教授 |
<評議員>
<相談役>
<顧 問>
8.歴代代表者
| 初代 | 工学博士 | 井上匡四郎 | 昭和29(1954)年4月~昭和34(1959)年3月 |
| 2代 | 石坂 泰三 | 昭和34(1959)年4月~昭和50(1975)年3月 | |
| 3代 | 土光 敏夫 | 昭和50(1975)年2月~昭和57(1982)年3月 |
| 初代 | 工学博士 | 辻 二郎 | 昭和29(1954)年4月~昭和43(1968)年10月 |
| 2代 | 工学博士 | 大越 諄 | 昭和43(1968)年11月~昭和44(1969)年10月 |
| 3代 | 工学博士 | 大山 義年 | 昭和44(1969)年10月~昭和52(1977)年7月 |
| 4代 | 理学博士 | 菅 義夫 | 昭和52(1977)年8月~昭和56(1981)年5月 |
| 5代 | 工学博士 | 福井 伸二 | 昭和56(1981)年5月~平成元(1989)年5月 |
| 6代 | 理学博士 | 宮島 龍興 | 平成元(1989)年5月~平成11(1999)年5月 |
| 7代 | 工学博士 | 佐田登志夫 | 平成11(1999)年5月~平成13(2001)年5月 |
| 8代 | 工学博士 | 吉川 弘之 | 平成13(2001)年5月~令和3(2021)年6月 |
| 9代 | 工学博士 | 山﨑 弘郎 | 令和3(2021)年6月~令和7(2025)年6月 |
| 10代 | Ph.D | 三島 良直 | 令和7(2025)年6月~ |
9.規程等
定款 ⇀住所
事務所
公益財団法人 大河内記念会〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-21-10-1501 (グランスイート虎ノ門)
電話 03-3501-2856 FAX 03-3501-2727
e-mail: kinenkai@okochi.or.jp
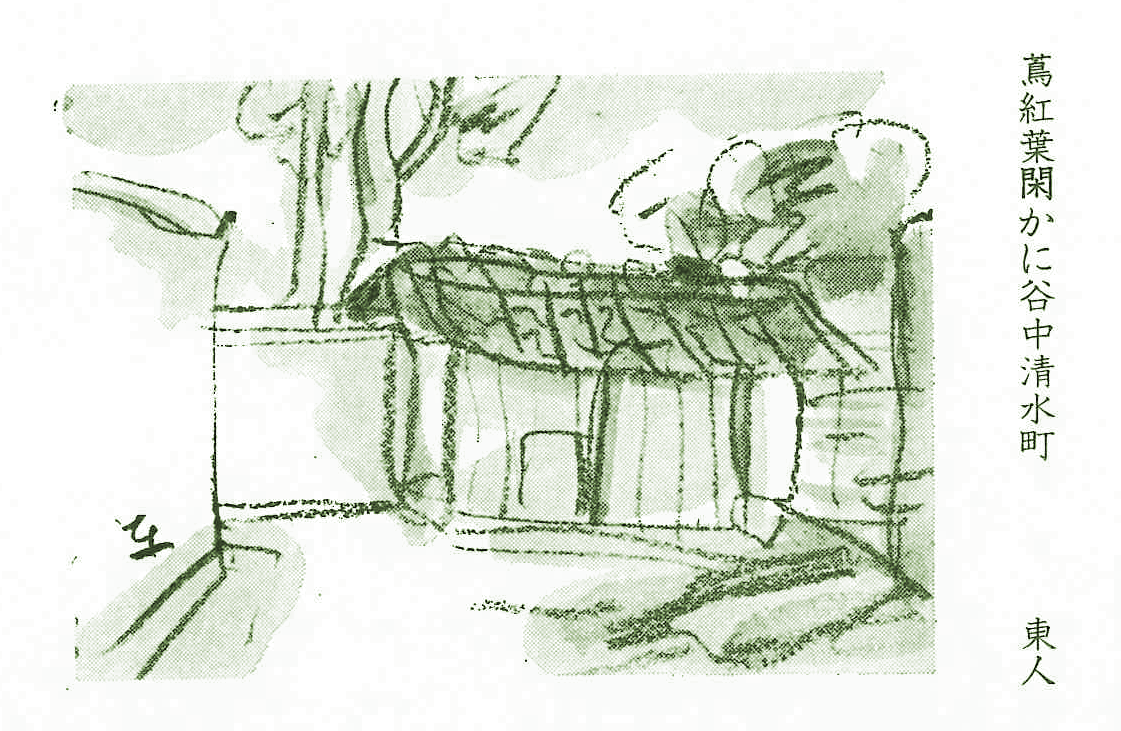
アクセス
地下鉄
- 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅 / 銀座線「虎ノ門」駅B2出口徒歩1分
- 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」駅 A12出口徒歩8分
- 都営地下鉄三田線「内幸町」駅 A3またはA4出口 徒歩12分
JR・ゆりかもめ
- 新橋駅 徒歩15分

 お問い合わせ
お問い合わせ